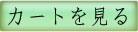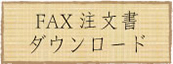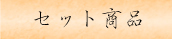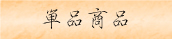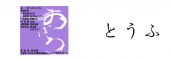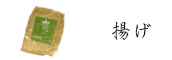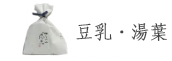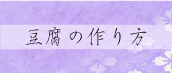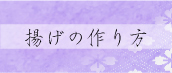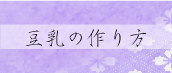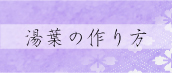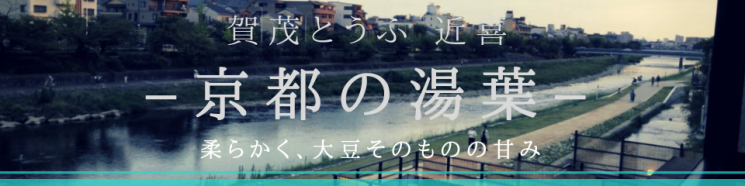
【今回ご紹介する商品】
![]()

湯葉とは、豆乳を温めて表面にできる膜のことです。牛乳を温めた時に張る膜をイメージ
していただくとわかりやすいと思います。
「畑のお肉」とも呼ばれる大豆の良質なたんぱく質がギュッと詰まっているのが特徴です
。
また、作るのに手間と時間がかかります。
具体的には、<豆乳を作る→豆乳を温めて膜が張るのを待つ(約10分)→引き上げる→豆乳
を温めて膜が張るのを待つ(約10分)→引き上げる→…>を繰り返し、数回引き上げると
膜が張らなくなるので豆乳そのものを入れ替えます。
そのため、たくさんの量を一度に作ることはできません。
ただし、乾燥させれば長期間の保存もでき、扱いもとても簡単になります。
![]()
“ゆば”というと、関東の方は「あれ?“湯波”じゃないの?」と思われるかもしれません。
“ゆば”で有名なのは、東は「日光」で西は「京都」ですが、日光では“湯波”、京都では“湯
葉”と書くのが一般的です。
そして、できあがった“ゆば”にも違いがあります。
日光では膜の真ん中からすくいあげるので、二枚重ねでボリュームのある“ゆば”になり、
京都では膜の端から引き上げるため、一枚の薄い“ゆば”になります。
当店は京都のゆばですので、“湯葉”としています。
ちなみに、中国では日常的に乾燥湯葉が使われていて、「豆腐皮(トウフ―ピー)」と呼
ばれています。
日本へ伝わったころは「豆腐上物(うわもの)」と呼ばれていたようで、豆腐作りと関係
が深いことが伺えます。それが、作るときに皺が寄ることから「豆腐姥(うば)」となり
、略して「姥(うば)」、なまって「湯葉(ゆば)」になった、との説があります。
![]()
湯葉は「肉の代わりとなる重要なたんぱく源」として、長く寺社で食されてきました。
日本への伝来は、「約1200年前(平安時代)に天台宗の開祖・最澄が中国への留学から帰
るときに一緒に持ってきた」とも「鎌倉時代に禅僧が中国から持ってきた」とも言われま
す。
いずれにせよ、良質なたんぱく質を摂るため、肉や魚を食べることを禁じられた修行僧に
食べられてきた、と言えます。そのため、京都や日光、そのほか奈良などの門前町が湯葉
の産地として有名になります。
その後、精進料理や懐石料理として湯葉は食べられてきました。
(実は当店も、初代は「湯葉喜(ゆばき)」を店名にして、湯葉作りで店を始めました。
豆腐作りが始まるのは三代目から、このときに「近喜(きんき)」と店の名前を改めます
。)
寺社が身近な京都では、家庭でも湯葉をいただきます。
ひとむかしでは、乾燥湯葉を煮物の具にしたり、具材を包んで揚げたり、黄色く色づけた
乾燥湯葉を金糸玉子の代わりにちらしずしにのせたり。
「栄養価の高い保存食」「よく味がしみ込む」「扱いやすい」などの理由かと思います。
冷蔵技術が良くなってからは、生湯葉も一般的になりました。
![]()
当店でも「巻湯葉」と「つまみ湯葉」の二種類の生湯葉を作っています。
「柔らかくて大豆そのものの甘みがする」のが特徴です。
湯葉好きの方はもちろん、湯葉は苦手…という方にも、ぜひお召し上がりいただきたいで
す。
湯葉が苦手な方は、「湯葉はゴワゴワして味がないから…」と思う方が多いのではないで
しょうか。
当店のポイントは大豆。賀茂とうふ 近喜では、甘みのもとになる糖分が多い大豆も使って
います。
手早く湯葉を作ろうと思えば、たんぱく質の多い大豆を使うのが一番です。簡単に湯葉が
張るからです。ただし、たんぱく質が多い分、「固い」食感になります。
そして、たんぱく質が多い大豆は一般に糖分が少ない傾向にあります。だから、「味がな
い」湯葉になってしまうように思います。
賀茂とうふ 近喜の「巻湯葉」と「つまみ湯葉」、ぜひお試しください!
【つまみ湯葉を使ったレシピ】
〇とろゆば
「つまみ湯葉」は豆乳に張った湯葉をすくいあげた生湯葉です。
大豆そのものの甘みがギュッと詰まっていますので、そのままお召し上がりいただくのがいちばん簡単でぜいたくです。

1.お椀に「つまみ湯葉」を入れます
2.わさび醤油をすこし垂らして、お召し上がりください
だし醤油に梅肉を添えてもおいしいです
〇生湯葉丼
あんかけや卵とじにするレシピが多いですが、「つまみ湯葉」がもつ大豆そのものの甘みをダイレクトに楽しむため、そのままごはんにのせるのをお奨めします。

1.お椀にやや少なめに温かいご飯を盛る(麦ごはんにしても良い)
2.「つまみ湯葉」を上からのせ、お好みで青ねぎ・のりを散らす
3. わさび醤油を上からかけて、そのままどうぞ
4.ひと手間かけるなら、だし汁をおすすめします
[だし汁(ひとり分)の作り方]
みりん 大さじ1、うすくち醤油 大さじ1/2、片栗粉 小さじ1、水 小さじ1を混ぜ合わせ、生湯葉丼に上からかける
【巻湯葉を使ったレシピ】
〇湯葉刺し
平らな湯葉を重ねて巻いた「巻湯葉」は、ボリュームがあり扱いやすい生湯葉です。
湯葉独特の食感を楽しみながら、大豆そのものの甘みを楽しむには、湯葉刺しがおすすめで
す。

1.「巻湯葉」をまな板にのせ、ひと口大に切り、刺身皿にのせます
2.刺身と同じようにわさび醤油をつけていただくのがおすすめです
〇巻湯葉のお吸い物
巻湯葉はボリュームがあるので、ひとくち大に切ったものを入れるだけで椀だねになりま
す

1.鍋にだし汁を煮立たせ、しいたけを入れて煮る
2.塩と醤油、酒を少々加えて、味を調える
3.椀にひとくち大に切った巻湯葉を入れ、2.で仕上げたおつゆを注ぎ、三つ葉を浮かせる
お好みでゆずの皮を添える
【今回ご紹介した商品】